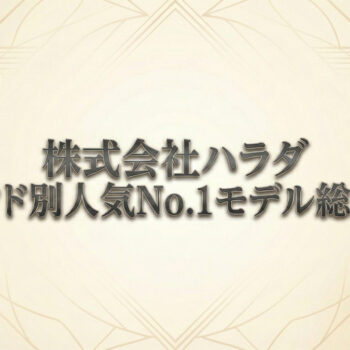2022年、シチズンは年差を誇るクォーツウォッチ「ザ・シチズン」において、初めて藍染された和紙文字板を採用した。そして2025年、同社は再び、この藍染和紙文字板を採用したコレクションを3本リリースし、シリーズに彩りを加えている。今回、3モデルの藍染和紙を手がけた徳島県の藍染工房「Watanabe’s」の渡邉健太さんにお話を伺った。

渡邉 健太
1986年、山形県生まれ。藍師。染師。藍染工房「Watanabe’s」代表。自らの手で藍の栽培から染色、製品化までの全てを手掛け、ジャンルを問わない幅広い手法で世界中に藍染の魅力を発信している。2021年、NHK大河ドラマ「青天を衝け」にて、藍染・蒅(スクモ)造りを指導。
ザ・シチズンの藍染和紙文字板モデルについては、以下もご確認ください。>>
「Iconic Nature Collection」AQ4100-22L

2025年、シチズンのフラッグシップであるザ・シチズンは、誕生30周年を迎えた。これを祝す30周年記念限定モデルのテーマは、日本最古の随筆である「枕草子」に見られる「をかし」の美意識である。現在、枕草子にならった、「春の明け方の情景」と「夏の夜の情景」をテーマにした2モデルが発表されているが、その夏モデルにあたるAQ4100-22Lには、「Watanabe’s」によって手がけられた藍染和紙文字板が使用されている。

今回の新作、枕草子の「夏の夜の情景」をテーマにしたモデル(AQ4100-22L)についてお伺いします。こちらの藍染和紙は、どのようなものなのでしょうか?
ベースとなる文字板には、これまでと同様、土佐の典具帖紙を藍染したものを使用しています。藍染和紙文字板を初めて採用したモデル(AQ4091-56M)のそれと、同じ工程で染めたものですね。藍染された和紙を下地に、模様が印刷された透明な上板を重ねることで、情緒的な夏の風景が表現されています。
色の濃さも初採用モデルと同じものですか?
同じですね。前作に比べて濃く見えますが、これは、上板の模様によるものです。本作の下地となる藍染和紙は、前作となるべく同じ濃さに染めています。

なるほど。前回のインタビューでは、藍の色合いは染液によって毎回変わるため、同じ色を出すのは難しいとお伺いしたのですが・・・。
そうですね。ただ、和紙(典具帖紙)と藍染との組み合わせによる発色のデータがたまってきたことで、色をある程度そろえられるようになりました。また、実際に量産する際には、毎回その時の染液で試作したものをお送りし、シチズンさんに、過去の製品と比べて濃度や透過率(エコ・ドライブに対する)といった点をチェックしていただいています。こうして、毎回の品質のコントロールを行なっています。
なるほど、これまでの積み重ねが生きているんですね。ちなみに、100周年記念モデルの藍染和紙で採用されていた筒巻き絞りと、似ているようでまた違った表情ですね。あの技法では、本作の濃淡の表現は可能なのでしょうか?

筒巻き絞りだと、典具帖紙のように非常に薄い紙では、もっと細かい柄になってしまうんです。今回目指したような、柔らかく大きな濃淡を出すには、上板に模様を印刷する今回の方法が最適だったと考えています。制作の際は、どこまでこちらでデザインコンセプトを表現できるかを、シチズンさんとのやり取りの中で詰めていきましたね。
シチズンさんとの継続的な連携があってこその表現なのですね。

そうですね。シチズンさんからデザインのイメージをいただき、私たちはその実現方法や技術的な可能性を相談しながら進めます。和紙についての理解度も増してきたことで、「次はこんな表現ができるのでは?」とアイデアを出し合い、試行錯誤しながら、表現の技術を掘り下げていきました。
和紙に対する理解度が増すことで、できることも増え、新たな文字板表現にもつながるわけですね。
シチズンさんの和紙文字板モデルも今回で第4弾になりますが、何度も同じ素材(典具帖紙)に取り組めるというのは、大きな強みですね。こういった継続した取り組みというのは、私たちの仕事では結構珍しいんですが、その分素材への理解度が増すことで、さまざまな表現を模索することができるんです。加えて、典具帖紙自体の品質が安定していることも、こうした挑戦を後押ししてくれたように思います。
藍染和紙文字板「勝色」 AQ4100-65M

誕生30周年を祝う年差±5秒エコ・ドライブの1本。「Watanabe’s」とのコラボレーションによって、藍染の中で最も濃い色とされる日本の伝統色、「褐色(かちいろ)」が表現されている。この色合いはその響きから「勝色」とも呼ばれ、武具や祝賀の品に用いられるなど、勝利への願いを託されてきた。光の当たり方で色の見え方が変わる、この神秘的な伝統色についてもお話を伺った。
こちらの新作のテーマは、「勝色(かちいろ)」だと伺っています。時計に限らず、ファッションシーンなどでも見られるテーマですが、本作ではどのようにアプローチされたのでしょうか? これ以上濃く染まらない、という限界の色とも聞きましたが。
勝色は、勝負事などでも取り入れられているポピュラーなカラーリングですが、化学染料やプリントなどで、その“色味”を表現したものがほとんどだと思います。今回私たちは、伝統的な藍染の技法を用いた染色で、よりリアルな勝色を表現することに挑戦しました。

藍染でよりリアルな勝色を、ですか。難しそうですね。
和紙は染め重ねていくと、本当に真っ黒になってしまうんです。蒅(すくも)を使った日本の藍は、青だけでなく、赤や黄、緑、茶などの色素成分が微量に含まれているのが特徴なのですが、濃くしすぎるとその藍ならではの微妙な色彩が消えてしまう。腕時計の文字板にしたときに「これ、何色?」となってしまうんです。

なるほど。ただ濃くするだけではない、と。
ええ。「勝色」というテーマを目指しつつ、発酵染色の、藍ならではの複雑な色合いや表情も失わないようにする。その両立を目指しました。濃すぎると藍らしさが消える、でも浅いと勝色ではない。何度も試作を重ねて、文字板として見た時に、赤や紫が感じられる、藍の持つ色の深みや複雑さと、「勝色」としての力強さの両方が感じられる、絶妙な濃度を探りました。
実物を見ると、和紙の風合いも残っていて、単なる濃紺ではない深みがあります。化学染料やプリントでは、この深みや複雑さはなかなか出ないでしょうね。数量限定モデルとのことですが、素晴らしい仕上がりに思えます。
自分でも、良い色だなと実感しています。ちょうど良い「藍も感じられる勝色」に着地できたんじゃないかと。

まさに、試行錯誤の賜物ですね。
そうですね。もちろん液の状態も発色に影響するので、染める回数だけでなく、浸ける時間なども細かく調整を行いました。ちなみに、新しい液を使うとより濃く染まりやすいですね。過去のデータも参考にしながら、試行錯誤を重ねました。

藍染和紙文字板「叢雲絞り染め」

こちらも誕生30周年を祝うモデル。「Watanabe’s」とのコラボレーションによって、和紙文字板に伝統的な絞り染め技法「叢雲(むらくも)絞り染め」を実現。空に浮かぶ雲のような幻想的な模様は、職人の感性によって生み出されており、同じ表情がふたつとない。デュラテクトDLCが施された艶やかかつ堅牢なブラックケースと、ブルーのレザーストラップを採用し、その唯一無二の美しさを際立たせている。
このモデルの藍染和紙文字板は、どのような技法で染められたものなのですか?
この藍染和紙には、伝統的な「叢雲(むらくも)絞り染め」という技法を使用しています。技法自体は、紙や布にしわを入れ、表情付けするだけのシンプルなものです。つまり、誰でもできる絞り染めなんですが、その分、しわの入れようによっては、表現にすごく幅が出せる技法とも言えますね。この藍染和紙では、その“しわの入れ方”に試行錯誤したのを覚えています。

シンプルな技法がゆえに、理想に近づけるのに難しいんですね。
まず、時計の文字板という非常に小さな面積に、自然で複雑な表情を出すのが難しい。かといって、あまりに均一に、きれいにしわを寄せすぎると、手作業ならではの偶発性や味が失われてしまう。面白いことに、性格が几帳面な人が担当すると、どうしてもしわが均一になってしまいがちなんです。むしろ、少し大雑把というか、良い意味で「適当」にできる人、その「塩梅」を出せる人が行った方が、自然で深みのある“味”が出やすいんですよ。
なるほど! 計算されていない、偶然性が叢雲染めの「味」になるのですね。
まさにその「塩梅」です。さらに、素材が非常に薄い典具帖紙なので、少し力を入れすぎるとすぐに破れてしまう。破れないように、かつ、細かく、それでいて自然に見えるようにしわを寄せる。この作業をひとつひとつ手作業で行います。「どうやってこんなに細かく?」と見る人に思わせるような、繊細さと複雑さを両立させるよう模索しました。

その絶妙なしわ寄せは、渡邉さんが担当されたのですか?
実はその日、その時の調子によって、一番うまくできる人が変わるんです。染色に関わる3人で、その日の朝に試しに全員でしわ寄せをやってみて、「今日は〇〇(スタッフ)のが一番いいね」となれば、そのスタッフが当日のしわ寄せ担当になる。そういう決め方をしています。
なるほど!面白いアプローチですね。

藍染和紙の制作は片手間ではできないので、しわ寄せ担当、染め上げた後に水の中で和紙を伸ばす担当といったように、スタッフ全員で分担して一気に作業をすすめます。基本的に、藍染和紙はチームでの合作となりますね。
臨機応変に、例えばジャズのセッションのように、全員でその日のベストに持っていくわけですね。
そうですね。出来上がりを見て、直感的に一番良い雰囲気が出たと思ったものを、落とし込めるようにしました。その瞬間の環境、作り手の気分や体調(前の日に奥さんと喧嘩したとか(笑))さえも出来上がりに影響するんですが、影響されやすいからといって「これでいいか」と妥協はせずに、その時々での「最高」を模索しましたね。
最後に

最後にお伺いしたいのですが、これまで手掛けられた藍染和紙文字板の中で、作り手として「これが一番」というのは、ずばり、どれになりますか?
いやー、難しい質問ですね(笑)。でも、あえて挙げるなら、「勝色」でしょうか。
勝色ですか! 理由を伺っても?
「勝色」と称する色合いは世の中に色々ありますが、色味を似せたものや化学染料、プリントなどによる表現がほとんどだと思います。今回のように、日本の伝統的な蒅(すくも)を使った藍で、真正面から本物の「勝色」を表現したこの和紙文字板は、現代における藍染において、本当に意義深いものだと思っています。

なるほど、本物ですか。熱いですね! 私もこの勝色モデルを推していこうと思います。もちろん、他のモデルもそれぞれに魅力がありますが。
そうですね、他のモデルにもそれぞれ物語や苦労がありますから、結局は選べない(笑)。最初のモデルも、筒巻き絞りも、今回の夏モデルも、それぞれに良さがあります。
なるほど、全てのモデルが子供のような存在ということですね。本日はお時間をいただき、誠にありがとうございました。

この記事の監修